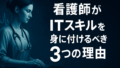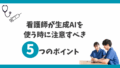はじめに
近年、ニュースやSNSで「ChatGPT」や「生成AI(Generative AI)」という言葉を耳にする機会が増えました。
「でもそれって看護師の仕事には関係ないのでは?」と感じる方も少なくないでしょう。
実際のところ、生成AIはまだ医療現場に直接導入されているわけではありません。しかし、看護師として日々の業務やキャリア形成を考えるうえで、生成AIを正しく理解しておくことは非常に価値があります。
なぜなら、
- 記録や資料作成の効率化
- 最新情報や学習のサポート
- 新しい働き方やキャリア選択肢の拡大
といった形で、看護の仕事や学びを後押ししてくれる可能性があるからです。
今回は「看護師が知っておくべき、生成AIの知識3選」として、基本から活用、そして注意点までを整理してご紹介します。
1.生成AIの基本を知る
まずは「生成AIとは何か?」を押さえておきましょう。
生成AIとは
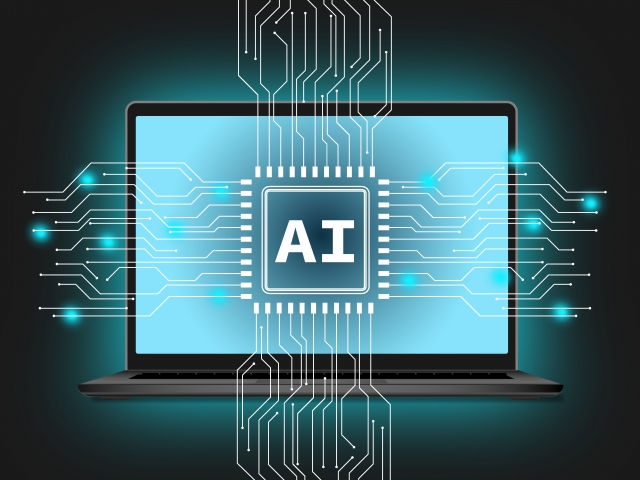
生成AI(Generative AI)とは、大量のデータを学習し、その知識をもとに「新しい文章・画像・音声・動画」などを生み出す人工知能の総称です。従来のAIが「データを分析して結果を分類・予測する」のが中心だったのに対し、生成AIは「ゼロから何かを作り出す」ことが特徴です。
代表例としては、文章を生成する ChatGPT、画像を描く Stable Diffusion や Midjourney、音楽を作るAIなどがあります。つまり生成AIは、一言でいえば「創造力を持ったAI」と表現できます。
これまでのAIは、例えば「この写真は猫か犬かを判別する」といった「識別・分類」に強みを持っていました。しかし生成AIは、「猫のイラストを描いて」と指示すれば新しい猫の画像を生み出し、「高齢者看護におけるリハビリの工夫をまとめて」と頼めば自然な文章を出力してくれます。
できることの具体例
- 看護記録やレポートの文章例を考えてくれる
- 医療英語の翻訳や英語論文の要約をサポート
- 学習計画を一緒に立てる
- プレゼン資料の構成や下書きを作成する
要するに、「頭の中のアイデアを整理する手助け」「下書きを効率的につくる補助役」として活用できます。

看護師にとってのメリット
看護師の仕事は「患者さんに向き合う時間」だけでなく、看護記録や報告書の作成、委員会活動、教育資料の準備など、文章を書く作業が意外と多いのが特徴です。臨床の忙しい合間に、限られた時間で記録や資料を仕上げなければならず、負担に感じている人も多いのではないでしょうか。
生成AIをうまく活用すると、この「文章をゼロから書く」負担を大幅に軽減できます。たとえば、
- 看護記録の定型表現を提案してもらう → バイタルサインや症状を入力すれば、自然な文章例を提示してくれる。そこから修正すれば記録が早く仕上がる。
- 患者指導の説明文をわかりやすく整える → 「糖尿病患者への生活指導を簡単な言葉で説明して」と指示すれば、患者さんに伝えやすい文章を作れる。
- 勉強や資格試験の効率化 → 苦手分野を入力すると、復習のポイントや暗記の工夫を提案してくれる。
- 英語論文の要約や翻訳 → 海外の最新文献を読むハードルを下げられる。
つまり、生成AIは「記録や資料作成のスピードを上げるツール」であると同時に、「学習やキャリアアップを支えるパートナー」にもなり得ます。
さらに、生成AIを活用できる看護師は、将来的に業務改善や教育の場面でリーダー的な役割を担える可能性もあります。
「AIを使って効率化する方法を知っている人材」というだけで、病棟やチームの中で頼られる存在になれるからです。
2.医療現場での活用可能性と限界
次に「実際の医療や看護の現場で、生成AIはどう使えるのか?」を考えてみます。
活用可能性
- 看護記録の下書き → 例えば「バイタル測定後の患者の状態」を入力すれば、文章例を提示してくれる。
- 教育・研修の補助 → 新人教育用のシナリオ、模擬問題の作成。
- 文献検索のサポート → 最新エビデンスの要約や英語文献の解説をしてくれる。
- 業務改善アイデア出し → 「記録の効率化」「患者教育の工夫」など、発想を広げるヒントになる。
しかし「限界」もある
- 誤情報(ハルシネーション)を含む → もっともらしい嘘を生成することがある。
- 診断や処方の判断は不可能 → 医療判断をAIに任せることはできない。
- 最新情報が必ずしも反映されていない → データの学習時期に限界がある。
重要な考え方
生成AIは「相棒」にはなりますが、「判断者」ではありません。
最終的な判断は必ず人間(看護師・医師)が行うことが大前提です。
3.セキュリティと情報管理
最後に、看護師として必ず押さえておきたいポイントが「情報管理とセキュリティ」です。

患者情報は入力してはいけない
生成AIはクラウド上で動いているため、入力内容が外部に保存される可能性があります。
カルテ内容や患者名など、個人情報をそのまま入力するのは絶対にNGです。
安全に使うための工夫
- 個人情報を伏せて要約した形で入力する
- 「〇歳女性、発熱あり」など匿名化する
- 院内のガイドラインやセキュリティ規則を必ず確認する
組織としての対応も始まっている
一部の病院や大学では、すでに「生成AIの利用ルール」が定められています。
今後、医療現場全体で「どのように安全にAIを取り入れるか」が重要なテーマになっていくでしょう。
まとめ
ここまで「看護師が知っておくべき、生成AIの知識3選」として、
- 生成AIの基本
- 活用可能性と限界
- セキュリティと情報管理
を紹介しました。
生成AIは、看護師の仕事を奪うものではなく、むしろ「日々の学びや業務を支えてくれる新しいツール」です。
ただし、「正確性」と「守秘義務」に注意しながら活用することが欠かせません。
これからの時代、生成AIを知っているかどうかで「仕事の効率」や「学びの深さ」に差がつく可能性があります。
ぜひ、看護師としてのキャリアアップや業務改善の一助として、生成AIを前向きに活用してみてください。
おわりに
看護師の仕事はこれからも「人と人との関わり」が中心であり続けます。
AIがどれだけ進化しても、患者さんに寄り添い、安心を与える役割は人間にしかできません。
だからこそ、AIを恐れるのではなく、味方につけて自分の強みにすることが大切です。
生成AIを理解し、正しく活用できる看護師は、これからますます価値が高まっていくでしょう。