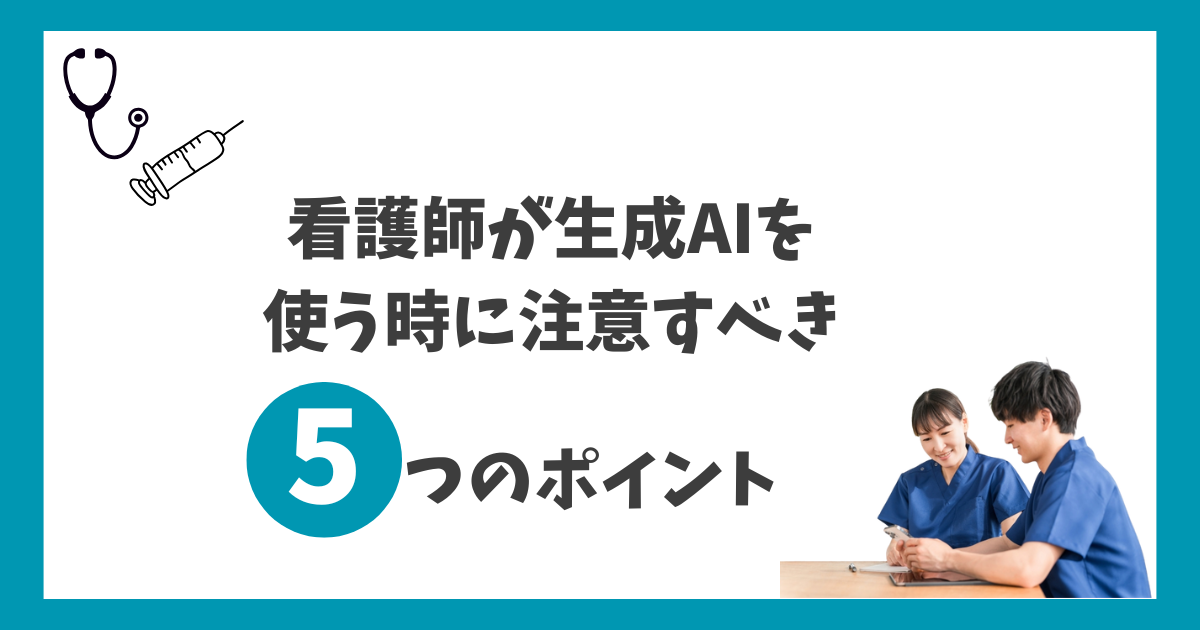はじめに
ChatGPTをはじめとする生成AI(Generative AI)は、ここ数年で急速に普及し、一般の人々の生活や仕事にも使われるようになってきました。文章の要約や翻訳、アイデア出しなど、看護師にとっても便利に感じる場面は少なくありません。
しかし一方で、医療現場は患者の命や安全に直結する場所です。生成AIを何も考えずに利用すると、思わぬリスクにつながる可能性があります。そこで今回は「看護師が生成AIを使うときに注意すべき5つのポイント」をまとめました。便利さを享受しつつ、安全に活用するための視点としてぜひ参考にしてください。
1.個人情報を入力しない
生成AIを使ううえで最も大切なルールが「個人情報を入力しない」ことです。
多くの生成AIサービスはクラウド上で動いており、入力した内容がサーバーに保存・解析される仕組みになっています。つまり、一度入力したデータは完全に削除できない可能性があり、思わぬ形で第三者に利用されるリスクがあります。看護師が患者情報をそのまま入力してしまうと、守秘義務違反や情報漏洩といった重大なトラブルに直結します。

入力してはいけない情報の例
- 患者の氏名、生年月日、住所、電話番号
- 入院日や病棟番号、診察券番号などの特定につながる情報
- 詳細な病歴やカルテの記載そのもの
例えば「〇〇病棟のAさん(72歳男性、肺炎で入院中)」と入力すると、それだけで個人が特定される可能性があります。これを外部サービスに入力するのは非常に危険です。
安全に使う工夫
- 個人が特定できない形に置き換える(「70代男性、肺炎入院中」など)
- 記録文例を考えるときは「仮想の患者像」として入力する
- 具体的な数値や日付は伏せ、一般化して利用する
守秘義務は看護師の基本的な責務です。便利さに流されて「ちょっとだけなら」と思うと大きなリスクにつながります。生成AIを活用するときは、常に「この情報を入力しても患者さんのプライバシーは守られているか?」と自問することが大切です。
2.出力内容は必ず確認・修正する
生成AIはとても自然な文章を出力してくれるため、「そのまま使えるのでは?」と思うかもしれません。しかし実際には、AIが出す情報には誤り(ハルシネーション)が含まれることがあります。
例えば、存在しない論文を「参考文献」として提示したり、正しいように見えて実際には間違っている医学知識を出力したりすることもあります。これをそのまま看護記録や発表資料に載せるのは非常に危険です。

実践のコツ
- 出力結果を必ず自分の目で確認する
- 信頼できる教科書や文献と照らし合わせる
- 「下書き」として使い、最終版は必ず自分で修正する
AIは便利な補助ツールですが、最終的な責任は人間にあるという意識を忘れないことが大切です。
3.医療判断には使わない
生成AIに「この症状ならどんな治療が必要?」と質問すれば、もっともらしい回答が返ってくることもあります。しかし、AIの回答をそのまま「診断」や「処方」に使うことは絶対に避けなければなりません。
生成AIはあくまで「学習したデータからパターンを推測して答えている」だけであり、最新の医学的知見やガイドラインに完全に準拠しているわけではありません。また、患者一人ひとりの個別性を考慮することもできません。

実践のコツ
- 医療判断は必ず医師や専門資格を持つ人間が行う
- AIの回答は「参考資料」や「説明補助」として使う
- 患者さんへの説明に利用する場合も、必ず自分の言葉で補足する
生成AIは「決める」ためのものではなく、「考えるきっかけを与えるもの」として捉えるのが安全です。
4.著作権や引用ルールを守る
生成AIが出力した文章や画像には、著作権上のグレーな部分が存在します。とくに看護研究や学会発表で利用する場合、出典を明示せずにそのまま使うと「盗用」とみなされる可能性があります。
また、AIが既存の文献や資料をもとに似たような表現を生成することもあるため、知らず知らずのうちに他人の著作物に依存してしまうリスクもあります。

実践のコツ
- AIが出した文章は参考にして、自分の言葉に書き直す
- 参考にした文献や出典は必ず明記する
- 画像生成AIを使う場合は「商用利用可能」かどうかを必ず確認する
研究・発表の場で信頼を損なわないためにも、著作権意識は常に持っておきましょう。
5.院内ルールやセキュリティポリシーを確認する
最後に忘れてはいけないのが、所属する病院や施設のルールを守ることです。
すでに一部の病院や教育機関では「生成AIの利用ガイドライン」を定めています。場合によっては、セキュリティや情報漏洩の観点から「使用禁止」とされていることもあります。個人の判断だけでAIを利用すると、トラブルや処分につながりかねません。

実践のコツ
- 院内ポリシーやマニュアルを必ず確認する
- 業務での利用が禁止されている場合は、プライベート学習に限定する
- 「便利だから」と安易に使わず、組織全体の方針に従う
医療現場はチームで成り立っているため、一人の行動が全体の信頼に影響します。
まとめ
生成AIは、看護師にとって学習や業務を支える強力なツールになり得ます。しかし、その便利さと同時にリスクも伴います。
今回紹介した5つのポイントは、生成AIを安全に活用するための基本ルールです。
- 個人情報を入力しない
- 出力内容は必ず確認・修正する
- 医療判断には使わない
- 著作権や引用ルールを守る
- 院内ルールやセキュリティポリシーを確認する
これらを意識して使えば、生成AIは「恐れるべきもの」ではなく「頼れる相棒」になります。看護師としての守秘義務や専門性を守りながら、新しい技術を味方につけていきましょう。